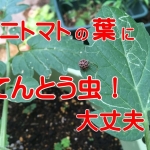トマトの葉を切る切らないの見極め方【葉切りと摘葉の違い】

トマトの葉を切るべきか切らないべきか判断が難しい時があると思います。
葉を切ってしまうことで、株が弱くなってしまわないか?ちゃんと実は収穫できるのか?など気になりますよね。
この記事ではまず、葉を切るか残すか迷うパターンを挙げた後に切るべきなのか、それとも切らずに残しておくべきなのかについて解説したいと思います。
もくじ(タッチすると移動します)
葉を切るべきか迷う3つのパターン
おそらく多くの方が以下のうちのどれかに当てはまると思います。
- 葉が茂り過ぎて果実に日光が当たってない→色付くか不安
- 葉が茂り過ぎて風通しが悪い→病害虫の発生が不安
- 下の方の葉(下葉)が黄色くなっている→切って良いのかわからない
葉切りと摘葉(てきよう)の違い
| 葉切り | 摘葉 | |
| ミニトマト | × | ◎ |
| 大玉トマト | ○ | ◎ |
トマト栽培で“葉を切る作業”は「葉切り(はきり)」と「摘葉(てきよう)」の2つに分けることが出来ます。
- 葉切り・・・葉が茂り過ぎている時、果実に日光が当たらないことで中が空洞果にならないようにするため
- 摘葉(てきよう)・・・果実を均一に色付かせる為・風通しを良くすることで病害虫の発生を防止するため
ミニトマト栽培で葉を切るべきケース

- 葉が茂り過ぎて風通しが悪い→摘葉
- 下の方の葉(下葉)が黄色くなっている→摘葉
家庭菜園でミニトマトを栽培する場合、葉を切るべきなのは「葉が茂り過ぎて風通しが悪くなっているとき」と「下葉が黄色くなっているとき」です。
葉が茂り過ぎて日光が当たっていないケースはミニトマトに限り特に気にしなくても赤く色付きます。(品種によって黄色・オレンジ・茶色・緑色などに色付く)
つまりミニトマトは「葉切り」をしなくても大丈夫です。
大玉トマト栽培で葉を切るべきケース

- 葉が茂り過ぎて果実に日光が当たってない→葉切り
- 葉が茂り過ぎて風通しが悪い→摘葉
- 下の方の葉(下葉)が黄色くなっている→摘葉
次に大玉トマトを栽培する場合は、ミニトマトと異なり葉が茂り過ぎて果実に日光が当たっていない時、葉切りをする必要があります。
葉が茂り過ぎて風通しが悪いとき、下の方の葉(下葉)が黄色くなっているときはミニトマト栽培と同様に摘葉(てきよう)します。
なぜ葉を切らなければならないのか?
では、先ほどから繰り返し出てきている次の3つについてそれぞれ掘り下げて解説したいと思います。
- 葉が茂り過ぎて果実に日光が当たってない→葉切り
- 葉が茂り過ぎて風通しが悪い→摘葉
- 下の方の葉(下葉)が黄色くなっている→摘葉
葉が茂り過ぎて果実に日光が当たっていないとき

大玉トマト栽培に限り、葉が茂り過ぎて果実を覆っているときは「葉切り」という作業をします。
ミニトマト栽培ではそもそも果実が小さくまた、中身のゼリー質も小さいため、通常の生育で葉が茂っている分には、敢えて果実を日光に当てるための葉切り作業をする必要はありません。
では、なぜ大玉トマト栽培で葉切り作業をする必要があるのかというと、果実に十分に日光が当たらないことで果実内部にあるゼリー質が発育しなくなるからです。
果実の外見はゴツゴツとしていて、中身は皮とゼリー部分の間にすき間ができた状態になります。
このような果実を専門用語で空洞果(くうどうか)と呼びます。
ゼリー質にはうまみ成分のグルタミン酸が多く含まれているため、発達していないと味が悪くなります。
葉が茂り過ぎて風通しが悪いとき

重なり合って茂っている葉を間引くことで風通しが良くなり、病気の発生(カビなど)や害虫の被害を予防できる可能性が高まります。
色々なサイトや本を読んでも「風通しが悪いと病害虫に被害に遭いやすい」とありますが、なぜなのか?までは書かれていません。
実際に野菜を栽培した人だとわかるのですが、家庭菜園初心者にとってはそのあたりもよく分かりませんよね。
葉が茂るということはたくさんの葉が重なり合うことを意味します。
そうすると、葉の枚数が少なく茂っていないときは風が通っていたのに、葉が密になり風が通り抜けないことで株周りが蒸れるようになります。
そして少し考えてもらうと分かりやすいのですが、お風呂のような蒸れた場所を、換気しないでおくとどうなりますか?
天井やお風呂の壁などに黒いカビが生えますよね。
カビは細菌なのですが、ジメジメした場所で活発になり増殖します。
実はこれと同じことがトマトの葉が茂った時に起こります。
トマトではカビが発生しやすい場所には害虫も寄ってきやすい傾向があります。
なので、葉を切ることは換気と同じ役目があるんです。
下葉が黄色くなっているとき

トマトの葉が黄色くなる原因は複数あるのですが、特に下の方の葉である下葉(したば)が黄色くなってきたら、放置せずに摘葉します。
枯れてきた葉をそのまま放置してしまうと病害虫発生の温床になってしまうため、見つけ次第取り除かなければなりません。
黄色くなる原因の多くは病気であったり、生育不良が関係しているのですが、下葉が黄色くなってくるのは葉が役目を終えたことで葉を落とす生理現象の1つであり、正常なことです。
役目を終えたとはどういうことかというと、葉は光合成よって糖分やデンプンなどの養分と酸素を作り出しています。
それにより葉の近くになっている実へ養分を届けるのですが、果実が色付き熟すともう葉の役目は終わります。
そのため色付いて収穫できる状態の実より下に生えている葉は切ってしまって構いません。
実より上にある葉はこれから必要になる葉なので切ってはいけませんが、下の葉は不要なのです。
成長したトマトの株をみればすぐにわかりますが、葉が無くなっていることがほとんどです。
それでも成長し続けられるのは、上に上に新葉が生えてくるからです。
葉を切ることで株が弱らないの?収穫できなくなる?
トマトの葉は太陽の光と水を利用して養分として使う糖分やでんぷんと酸素を作り出しています。
そのため、葉が無ければ株は成長できず、当然花も咲かなかったり実が成らない結果になります。
しかし、過繁茂(かはんも)といってあまりにも葉が茂り過ぎている状態だとゼリー質の詰まった果実が出来なかったり、病害虫の発生、着色不良などが起こります。
ですので、葉を取っても枯れずちゃんと収穫まで至る具体的な葉の取り除き方を説明します。
葉切りのやり方

繰り返しますが、葉切りは主に大玉トマト栽培において、葉が茂り過ぎて果実に日光が当たっていないときに行う作業です。
手順として青い小さな実が成った約10日後頃に果実が見えるように葉を切ってください。
重なっているところを間引いて日光が当たるように調整します。
実が着いて25日後頃に葉が実を覆ってしまっている場合は、果実が見えるように葉を1/2ほど切ってください。
葉の先端が無い葉ばかりになって見た目は変ですが、目的は日光を当てることなので問題ないです。
このように青い実が十分に日光を浴びられるようにしておきましょう。
摘葉(てきよう)のやり方

摘葉(てきよう)はミニトマト、大玉トマト共通して行う作業です。
まず、天気のいい日に作業して下さい。雨の日に行うと傷口が乾きにくく、灰色かび病などの発生予防になります。
タイミングとして青い実が赤や黄色などに色付き始めたら、実が成っている房の付け根付近にある葉2枚だけを残し、それ以外の葉はすべて摘葉(てきよう)します。
またハサミは使用せず、手で折って葉を茎の付け根から取り除いて下さい。
ハサミを使うと切り口から病原菌が侵入しやすくなるのですが、もしハサミを使用するのであれば茎の付け根から5㎜程度残して切ってください。
収穫の最盛期を終えて8月後半になると株の高さは2m近くなるため、株全体に水や養分を行きわたらせる体力が残っていません。
そのため、葉は最低20枚以上残し、敢えて水分の蒸散量をあげて水を吸い上げるパワーを維持して下さい。
まとめ
この記事ではトマトの葉を切るべきか切らずに残しておくべきかについて説明してきました。
ただ、園芸学的に分類しているだけで、葉切り作業も摘葉作業もどちらも葉を取り除くことには変わりありません。
- 葉が茂り過ぎて果実に日光が当たってない→葉切り=大玉トマトのみ
- 葉が茂り過ぎて風通しが悪い→摘葉
- 下の方の葉(下葉)が黄色くなっている→摘葉
大玉トマト栽培のみ葉切りは必要であり、ミニトマト栽培では必要ありません。
| 葉切り | 摘葉 | |
| ミニトマト | × | ◎ |
| 大玉トマト | ○ | ◎ |
ぜひこの記事を参考にして葉切りと摘葉を実践してみて下さい。
トマト栽培特集!
イチゴの月別!栽培方法
| 10月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| | 11月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |
| 12月1月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 冬のイチゴの育て方! 2月の時期の作業と栽培方法 | |
| 3月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 4月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| | 5月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |
| 6月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 7月8月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 9月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |