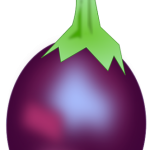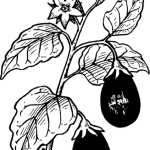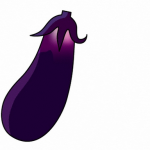ナスの育て方|畑で初心者が栽培できる方法を写真解説

人気野菜ランキング上位3位以内に入るナス。
この記事では0から自宅のお庭や市営農園などの空いているスペースを使ってナスを栽培する方法を紹介します。
ナスの種類は中長ナスの王道品種「千両二号」です。
春に植えて夏に収穫、株を更新して秋ナスまで収穫できる全ての作業を順番に説明します。
もくじ(タッチすると移動します)
- 1 ナス栽培基本データ
- 2 ナスの栽培時期と収穫までの流れ
- 3 ナス栽培で用意するもの
- 4 ナスの主な品種
- 5 ナスの植え付け前の準備
- 6 ナスの苗選び
- 7 苗の管理
- 8 植え付け(うえつけ)
- 9 着蕾(ちゃくらい)
- 10 開花(かいか)
- 11 茎の誘引
- 12 支柱立て(しちゅうたて)
- 13 整枝(せいし)・わき芽かき
- 14 着果(ちゃっか)
- 15 水やり
- 16 追肥(ついひ)
- 17 土寄せ(つちよせ)・中耕(ちゅうこう)
- 18 害虫対策
- 19 病気対策
- 20 下葉取り(したばどり)
- 21 収穫(しゅうかく)
- 22 更新剪定(こうしんせんてい)
- 23 秋ナスの収穫
- 24 調理
- 25 株の後片付け(かぶのあとかたづけ)
- 26 Q&A
- 27 まとめ
ナス栽培基本データ
ナスはインド原産の高温多湿に強い野菜です。つまりトマトと反対で乾燥に弱い野菜だということを覚えておいてください。
| 科名 | ナス科 |
| 原産地 | インド |
| 食用部分 | 果実 |
| 連作障害 | あり(4~5年空ける) |
| スタート方法 | タネ、苗 |
| 栽培期間 | 4~10月(中間地) |
| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |
| 生育適温 | 23~30℃ |
| 発芽適温 | 25~30℃ |
| 株サイズ | 幅60㎝ 高さ80~100㎝ |
| 株間 | 60㎝ |
| 列間 | 60~70㎝ |
| 畝幅 | 120㎝(2株植え) |
| 病気 | うどんこ病等 |
| 害虫 | アブラムシ、ハダニ、ニジュウヤホシテントウ、ハモグリバエ等 |
ナスの栽培時期と収穫までの流れ

| 地域 | 植付け | 収穫 |
| 中間地(関東甲信・東海・近畿・中国・九州北部) | 4月下旬~5月中旬 | 6月初旬~10月中旬 |
| 北海道・東北 | 5月下旬~6月中旬 | 7月初旬~9月下旬 |
| 四国・沖縄・九州南部 | 4月中旬~5月初旬 | 5月下旬~10月下旬 |
寒冷地・中間地・暖地の区分
中間地・・・関東甲信、東海、近畿、福井県、中国、九州北部
暖地・・・・四国、九州南部、沖縄県
ナス栽培で用意するもの
- クワ
- スコップ(ショベル)
- 土壌酸度計
- 苦土石灰など
- 完熟牛ふんたい肥
- 肥料(元肥)(化成肥料/有機質肥料)
- ポリマルチ
- ナス苗
- 支柱 長さ1000㎜~1800㎜ 太さ16~20㎜
- 肥料(追肥用)(固形肥料/液体肥料)
- 殺菌殺虫剤
- 噴霧器
- 園芸用ハサミ
- 散水用ホースリール/ジョーロ
ナスの主な品種

| 品種名 | 特徴 | 種苗会社 |
| 千両二号 | 1963年発表、高品質で収穫量が多い | タキイ種苗 |
| とげなし千両二号 | 2007年発表、茎葉やヘタにとげがない | タキイ種苗 |
| 黒陽 | 極早生の収穫量が多い長ナス | タキイ種苗 |
| 庄屋大長 | 長さ40㎝程になる大長ナス | タキイ種苗 |
| 黒福 | 皮が柔らかい中ナス | サカタのタネ |
| たくさん中長ナス | 早生種で皮が柔らかい | サントリーフラワーズ |
| 万寿満(マスミ) | 緑色で生食や煮物に向く | カネコ種苗 |
ナスの植え付け前の準備
- 菜園スペースを決める
- ナスの土作り
- 土壌酸度調整(どじょうさんどちょうせい)
- 元肥入れ(もとごえいれ)
- 畝立て(うねたて)
- マルチ張り
詳しい手順はこちらの記事
>>家庭菜園の土作りの順番を初心者に解説!庭の空き地を畑にする方法で確認して下さい。
ナスの苗選び

- 接ぎ木苗を選ぶ
- 茎が太くてしっかりしている
- 葉色が濃くてシャキッとしている
- 病害虫の被害にあっていない
- 節間(せっかん)が詰まっている
- 双葉が付いている
- 一番花のつぼみが付いている
- ポットの底穴から白い根が見える
ホームセンターなどに行くと「千両2号」や「黒陽」「庄屋大長」など様々な品種のナス苗が販売されていますが、まず初心者に選んでほしいのは品種は何でも良いですが必ず「接ぎ木苗」です。
接ぎ木苗とは主に病気などに強い丈夫な品種に収穫量が多い家庭菜園向きの品種を接(つ)いだ=くっつけた苗です。
以下写真の場合苗についているクリップより下が病気などに強い丈夫な品種、クリップより上が家庭菜園向きの栽培品種です。

なぜ接ぎ木苗を選ぶべきかというと、丈夫で品質の高い実がたくさん収穫できるからです。
接ぎ木苗ではない苗は実生苗(みしょうなえ)と呼ばれます。実生苗はタネから栽培した苗のことで価格が安いのですが、連作障害といって何年も同じ場所でナス科の野菜を栽培していると起こる障害が出ることがあります。
ですので、家庭菜園にて1株~2株程度栽培するのであれば迷わず「接ぎ木苗」の購入をおすすめしています。
そして、あとは節と節が間延びしていなくギュッと詰まっているものなどありますが、実際のところ、4月、5月に流通しているものには双葉や一番花のつぼみが付いている苗は少ないです。
おそらくポットから白い根が見える苗も少ないでしょう。これらは成長している証なので6月、7月以降に流通している苗の方が見つけやすいかもしれません。
苗の管理

冒頭のナスの栽培データでもお話ししましたが、ナスはインド原産の高温多湿に強い野菜です。
生育適温も23~30℃と高いです。
気を付けたいのはナスの苗は4月中には出回りますが、すぐに植え付けないことです。沖縄など一部の温暖な地域を除けば4月はまだ気温が低い日もあり、早めに植え付けてしまうと寒さで苗がダメになってしまうことがあります。
ですので、気温が高くなる5月の中旬までポット苗のままで管理をし、その時期以降になったら植え付けましょう。
もし、初めてナスを栽培するのであれば苗の購入は4月にせず、5月、6月に入ってからの方が良いです。
6月~7月以降になると花芽がいくつも付いた少し株が大きくなった立派な苗も出回るので、このくらいの苗であれば確実に実がなりますし、10月まで楽しめます。
植え付け(うえつけ)
土作りが整ったマルチに穴を空けます。ちなみに私は最初から穴が開いている「穴あきマルチ」を使っているため、穴の開いている場所の土をスコップで掘ります。

土を掘る深さは苗の株元の高さとマルチ穴が水平になる程度です。

深すぎても浅すぎても生育不良の元になるのでしっかり守って下さい。
同時に短めの支柱を「仮支柱」として株の脇に立てます。
水やりをしてとりあえず植え付け作業は完了です。
着蕾(ちゃくらい)
成長した苗に最初の蕾(つぼみ)がつき始めます。
ちなみに着蕾(ちゃくらい)という日本語はありません。中国語で『つぼみ』そのものを意味する言葉ですが、この記事では“つぼみを着けること”を便宜上「着蕾」と表記しています。

アップした写真がこちら。

開花(かいか)
一番最初に着いた蕾の花が咲きました。一番最初に咲く花を「一番花(いちばんか)」と呼びます。
薄紫色のきれいな花です。

茎の誘引
茎が伸びてきたら、支柱に茎を留めます。麻ひもで8の字結びをしても良いのですが、最近は支柱と茎を同時に挟んで留める「くき止めクリップ」が売っています。

支柱の太さに合ったものを購入して下さい。
実際に使い方は以下です。右側の方の支柱とナスの黒い茎が緑色のクリップで挟ませているのがわかると思います。

茎を傷つけずに誘引できる便利グッズです。
茎が成長するにしたがってどんどん増やしていきます。
支柱立て(しちゅうたて)

ナスは高さ100㎝程度までしか伸びないので支柱サイズも以下の通りでOKです。
支柱のサイズ
- 長さ:1000㎜~1600㎜
- 太さ:16~20㎜
今まで見てきた通り、私の場合は先に仮支柱を立て、株が成長してから本支柱と呼ばれる支柱を立てます。
苗を植え付けと同時に本支柱を立てても構いません。
苗元から10~15㎝程度離れた場所に垂直に1本立てます。
この後、わき芽を伸ばして3本仕立てにするのですが、そこでまた2本追加します。
整枝(せいし)・わき芽かき
一番花(いちばんか)が咲いたら整枝(せいし)といってナスの枝を3本に分かれさせる作業をします。
そのために「わき芽かき」という作業が必要になります。
整枝の作業は本などでは綺麗に3本に分かれた図解で示されているのですが、実際はそう上手く行かない場合もあるので以下の写真で説明します。
まず、一番花が咲いた状態の写真です。

同じ写真に解説を加えます。

ナスの枝を3本に分かれさすために、一番花の下にある2本のわき芽を残します。
上写真では一番花のすぐ下にある右側のわき芽は既に枝に成長しているのでこれをこのまま側枝(そくし)2として伸ばします。
そして、左側にあるわき芽を残し側枝3として伸ばします。
真ん中に伸びている枝を「主枝(しゅし)」1とし、側枝2、側枝3の合計3本に整枝できました。
側枝3より下にあるわき芽は全て摘み取ります。
また主枝や側枝2、側枝3が成長するとそこからわき芽が出てきます。

わき芽が成長して伸びる段階で以下のように側枝2、側枝3用の本支柱をバッテンにして立てます。

できれば収穫を終えるまでそれらのわき芽も摘み続けるのですが、株が大きく成長してくると訳が分からなくなり、知らないうちに側枝が伸びてしまうことがあります。
その場合は無理に切らず、個人的にはそのまま栽培してもいいと思っています。
プロの生産者ではありませんし、「失敗した(´;ω;`)」と落ち込むことでもないので家庭菜園で栽培して収穫する分には特に気にしなくてもいいでしょう。3本に整枝して栽培した方がベターだよくらいに考えて下さい。
着果(ちゃっか)
一番花(いちばんか)が終わり落下します。

花が落ち、ヘタになる部分のガクだけが残っている状態です。

今度は子房が膨らみ、実になり始めます。

そして一番最初になった実を一番果(いちばんか)と呼びます。
写真の大きさで5㎝程度です。

そして次になる実のことを二番果(にばんか)と言います。
写真の大きさで10㎝程度です。

一番果と二番果は大きくなるまで株に成らせておかず、どちらも長さ8~10㎝程度になったら収穫してください。
なぜ早めに収穫するのか?というと株全体の成長に養分を集中させ、結果的にたくさん実が収穫できるようにするためです。
実を成らせるためにはエネルギーと養分を使います。一番果、二番果を成らせっぱなしにしておくと養分が分散されてしまい、株全体の成長に回したい分まで使われてしまうからです。
水やり
ナスは高温多湿を好む野菜で原種はジメジメした場所に生育しています。
なので、水が大好きなので乾燥に弱い野菜です。
水が足りている状態
葉がシャキッとしています。

水が不足し始めている状態
やや葉が下向きになっているのがわかると思います。

ミニトマトと同じように栽培しているとナスは硬くなってしまったり実が成る前に花が落ちてしまうなどの問題が起こります。
真夏などは過乾燥にならないように、根元だけでなく、害虫対策も含め株全体にシャワーで水をかけることも大切です。

追肥(ついひ)
ナスは“肥料食い”と言ってたくさん肥料を必要とする野菜です。
だからといって一度にたくさんの量を与えるのではなく、追肥といって定期的に肥料を欠かさず与えるということです。
植え付けの1か月後から2週間ごとに肥料を与えます。
1回目はまだ苗が小さいのでマルチの穴に約3グラム程度の肥料(化成肥料の場合)を与えます。
そして、さらに2週間経過したら今度は、マルチを剥がし畝の両側に肥料30g/㎡(化成肥料の場合)をまきます。

ちなみに私は化成肥料ではなく、実付きを良くするためにリン酸成分のバッドグアノと醗酵魚粉を混ぜてまいています。
有機質肥料はしっかり混ぜてまかないと、虫が来たり猫などに踏み荒らされるので注意してください。
土寄せ(つちよせ)・中耕(ちゅうこう)
また追肥に関しては同時に、土寄せ(つちよせ)と中耕(ちゅうこう)という作業も同時にします。
- 土寄せ・・・肥料と土を混ぜ合わせて株元の土をならし、畝を作り直す
- 中耕・・・畝の周りの通路を耕し、通気性を良くする
ナスの根は株の真下だけに伸びるわけではなく、四方八方に伸びています。マルチを剥がし、畝周りの肥料をまくのはナスの根の先端から肥料を吸収させるためです。

肥料を混ぜて土寄せ、中耕をします。

畝周りをクワで耕すことで、硬くなった土がほぐれ水分や肥料が吸収しやすい土質になり、通気性がいい環境にもなります。
害虫対策

乾燥した場所に発生するハダニなどの害虫を防ぐためにシリンジといって葉っぱの表裏に水をかけて防ぐこともできますが、
基本的に、私は天然由来成分の殺虫殺菌剤である住友化学園芸の「アーリーセーフ」を散布しています。
ヤシ油の粘着性を利用して害虫駆除する仕組みなので、有機JAS規格=オーガニック栽培で使えます。
で、さらにナス科野菜の害虫として下写真のニジュウヤホシテントウ(28星テントウ)がいます。(ピンボケしてしまってすみません_(._.)_)

別名テントウムシダマシといって私たちが知っているアブラムシを食べてくれる益虫の「ナナホシテントウ」「ナミテントウ」とは違い、むしろ葉を食害する害虫です。

見分け方は簡単で害虫である星が28個あるからニジュウヤホシテントウと言います。
やけにたくさん星があるなぁと思ったら害虫のテントウムシなので即、取って駆除して下さい。
病気対策

上写真はうどんこ病にかかったメロンの葉の様子ですが、ナス栽培でも同じくうどんこ病にかかることがあります。
葉が白っぽくなる糸状菌(しじょうきん)でカビの一種です。
あとは高温で乾燥した場所を好むので水やりや害虫対策のところでも紹介しましたが、シリンジとって葉っぱに水をかけることで乾燥を防ぎ、ハダニを防止しましょう。
病気の場合は畑のそばにある植物から風に乗って来ることもあるので、自分の力だけでは完全に防ぐことができません。
カビなどが発生しないように茂り過ぎた葉を間引いたり、対策はあるのですがそれでも難しいこともあります。
できる限りの病気にかからないように、天然由来成分の殺虫殺菌剤「アーリーセーフ」などを定期的に散布をするなど、事前対策に力をいれておきましょう。
下葉取り(したばどり)

写真では少し分かりにくいのですが、株の下の方にある汚い葉は切り、風通しの良くスッキリさせて下さい。
雨や水やりなどによる泥はねによったカビ等の病気の発生防止につながります。
実より下の葉はもう成長に必要ないので、取ってしまって構いません。
収穫(しゅうかく)
開花後20~25日、だいたい6月くらいから実を収穫できるようになります。
下写真のように次から次へと実がなるので、千両2号など一般的にスーパーで販売されているナスのサイズ(だいたい15~20㎝くらい)になったらヘタの上を茎からハサミなどを使って収穫します。

更新剪定(こうしんせんてい)
ナスは高温多湿に強い野菜なのですが、気温が30℃以上を超える日が続くとだんたん株が疲れてきて実が付きにくくなります。
秋ナスなど、10月までナスを収穫するには一旦、茂っている枝葉を切り詰めて養分を使い過ぎないようにし、夏を乗り越えさせる必要があります。
作業の時期は7月下旬~8月上旬にかけてです。
下写真1枚目は7月の株の様子、2枚目は8月前半の株の様子です。

↓8月前半の株の様子
1枚目の生き生きした様子と比較すると、葉数も減り、だいぶ株が疲れています。

では、実際の更新剪定(こうしんせんてい)の手順を紹介します。
まず、草丈の1/2~2/3の長さになるようにハサミで株を切り詰めます。

結構たくさんの葉を切ります。

↓草丈の1/2~2/3の長さに切り詰めた後。
随分寂しい姿になりました。。

次に、株から約30㎝くらい離れた場所に1周、数か所にスコップを刺し込んでください。
これは“根切り”という作業で、伸びすぎた根を切り、肥料が吸収しやすいようにして、株を再生させる目的があります。

刺したすき間に30g/㎡に化成肥料や実付きを良くするリン酸成分のバッドグアノや発行魚粉などを追肥します。
化成肥料でも構いません!
そして水をたっぷりとあげて下さい。

やがて切った場所の脇から新芽が出始めます。
更新剪定(こうしんせんてい)という名前の通り、剪定する=(切る)ことで株が更新されました。

ぐんぐん伸びますよ

少し色が薄いですが花が咲き始めました!
花色が薄い原因は水分不足、肥料不足によって株にストレスがかかっている状態なので、この後もしっかり水やりと追肥を欠かしません。

もう一度、切り詰める前の株全体の様子をご覧ください。

そして20日程度経って成長した株の様子です。
見事に再生しました。

切り詰めた部分の脇から左に伸びる枝もだいぶ丈夫になっています。
緑色の柔らかかった茎が木質化(もくしつか)といって硬い枝に変わっています。

秋ナスの収穫
9月に入った秋ナスの様子です。
6月~8月に収穫したナスと同様、次から次へと実っています。

立派な秋ナスに成長したら収穫です。
色もツヤツヤとした“ナス紺色”になっていますね。

調理
収穫したナス「千両二号」を調理してみました。
調理といっても今回は皮をむいて焼くだけの「焼きナス」です。
下写真に写っているピーマンもナスのとなりで栽培したものです。
詳細は>>畑栽培のピーマンの育て方|庭の家庭菜園で初心者ができる方法

まずはナスをカットしてみました。

家庭菜園で収穫したナスとしては上出来です。

皮をむいて焼きナスを作りました。
千両二号は硬すぎず、柔らかすぎないどんなナス料理にも合う品種です。

かつお節とお醤油をかけて出来上がりです。
柔らかくてとても美味しかったですよ!

株の後片付け(かぶのあとかたづけ)
10月に入り、苗を植え付けてから半年経ちました。6月、7月、8月、9月、10月とたくさんのナスを収穫できましたが、さすがにご覧の通り、株が疲れ切って終わりを迎えようとしています。

実付きも悪くなり、小さくなってきました。
追肥や水やりをしても10月いっぱいでナス栽培は終了です。

10月になって最後の実を収穫したら、株を根元から切ります。

マルチを片付け、株を掘り上げて終了です。

根を掘り上げたら、来年のために土を休ませるのが良いですね。
そして、新しく野菜を植える前にまた土作りをしてください。
Q&A
Q:ナスの皮が固いのですがなぜですか?
A:>>栽培しているナスの皮が固くて苦い理由は?美味しいなすの育て方
Q:ナスは肥料が好きだと聞きました。どのくらいの間隔であげればいいのですか?
A:>>【ナスの花を見ればわかる!】追肥のタイミングと育て方
Q:プランターでも栽培したいのですが畑栽培との違いを教えてください。
A:>>ナスの育て方!プランターで初心者が栽培できるコツと方法
まとめ

ナスの畑栽培のコツ
- 5月以降に植え付ける
- 一番果は早く収穫する
- 追肥を欠かさない
- 更新剪定(こうしんせんてい)で秋ナス収穫に備える
ナスは初心者の方でも水切れと肥料切れさえ注意すれば、6~8月までは順調に栽培することができます。
しかし、9~10月の秋ナスまで収穫を楽しむのは「更新剪定(こうしんせんてい)」などちょっとした育て方のテクニックを知らないと上手く収穫できません。
今回は、実際に私が5月に植えて10月まで栽培&収穫した様子をたくさんの写真を使って解説しました。
同じように栽培すれば今年初めてナスを畑で栽培する方でも収穫することができるので、ぜひ参考にしてもらえると幸いです。
トマト栽培特集!
イチゴの月別!栽培方法
| 10月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| | 11月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |
| 12月1月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 冬のイチゴの育て方! 2月の時期の作業と栽培方法 | |
| 3月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 4月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| | 5月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |
| 6月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 7月8月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 9月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |