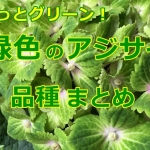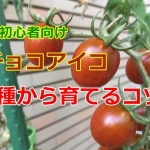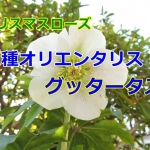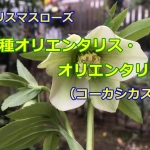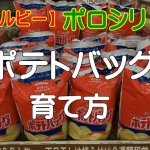プランターに植えた花がすぐ枯れてしまう原因と対処方法

ご近所のプランターに植わっているお花は長くきれいに咲いているのになぜかうちのプランターだけ植えても1ヶ月以内には枯れてしまう。。。
ネットや本で一生懸命勉強しているのになぜか上手く育てられない。。そう悩んでいるのはあなただけではありません。
今回はプランターに植えた花がすぐ枯れてしまう原因と対処方法を解説します。
もくじ(タッチすると移動します)
初心者が花を枯らしてしまう原因
苗選びの問題

弱々しい苗を選んでいる
まず毎回毎回弱々しい苗を選んでしまうということはないと思います。
ただ、たくさん花が咲いている苗よりもなるべくつぼみ多いものを選んでしまったり、大きくしたくないからできるだけ小ぶりな苗を選んでしまうことがあります。
対処法
切り花と違い根が付いている苗や鉢植え花の場合は、次から次へと花を咲かせるのであえてつぼみが多いものを選ぶより、茎が大きく、太くしっかりしていて葉もだらりとせず元気がいい、今たくさん花が咲いているものを選びましょう。
生育環境が違う花同士を一緒に植えている
違う種類の花同士を一緒に植えるときにありがちなのが、生育環境の違う植物を選んでしまうことです。
極端な例ですが乾燥した土を好む多肉植物と湿地を好むシダ植物を一緒に植えてしまうケースです。
対処法
寄せ植えなど違う花同士を一緒に植えるときは、原産地が近いものを選ぶことです。しかし素人ではそんなことよくわからないです。
なので売り場の人に聞くか、もしくは寄せ植え本や見本と同じ花の組み合わせを選ぶか、または「暑さに強い花」などとネット検索すれば最適な組み合わせがわかるので参考にします。
プランター選びの問題

プランターサイズと苗や株の大きさが合っていない
ちょうどいいサイズがないからといって植えた苗の量や株の大きさが合っていないと水やりの観点から上手く成長できないことがあります。
対処法
植える苗の量や株の大きさに対してひと回り大きいサイズのプランターを選びます。
排水性が悪いプランターを使っている
鉢底に穴が開いていないプランターや、プランターサイズに対して排水口が小さすぎる設計のものだと水はけが悪いため根が腐ります。
対処法
オシャレな鉢カバーとして使う目的として作られたものや、単純に設計が悪い商品がは選ばないようにしましょう。
植え方の問題

プランターに土を入れ過ぎている
目一杯入れてしまい土が溢れてしまうと水やりのときに泥が跳ねかえって病気の原因になったり、茎が腐ることがあります。
対処法
鉢の上から2~3㎝下のところまで入れてスペースを空けておきましょう。水をやったときに土が上がってもあふれないスペースなので「ウォータースペース」といいます。
苗を植える高さが間違っている
土の入れすぎに共通しますが、本来土に埋めない高さまで土を入れてしまい茎が腐ってしまうことがあります。
対処法
苗や鉢植え花を植えるときは、元々ポットや鉢に植わっていてた高さと同じ高さのところで水平に植えます。
たくさんの苗を植えすぎている
プランターサイズに対して苗の量が多すぎるケースがあります。例えば隣の苗と苗の間がギュギュウで根が伸びるスペースがないなどです。
対処法
苗を植えるときは隣との間隔は苗1個分が基本です。植えた時は淋しく感じますが、株が成長することを考えて植えましょう。
土の問題
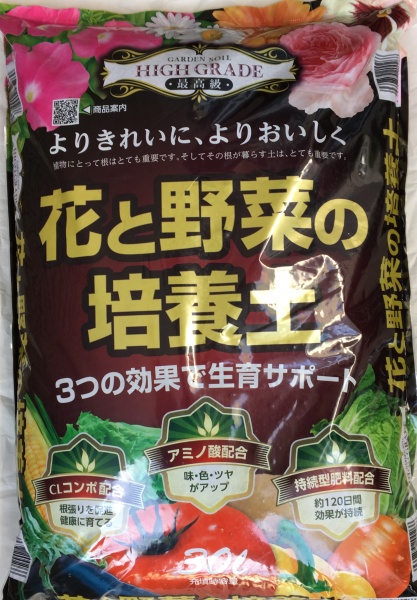
培養土を使っていない
土選びは重要です。土にはさまざまな種類があり赤玉土と腐葉土など組み合わせて使うことで花栽培に適します。ただ、初心者であればめんどくさいです。
対処法
初心者で上手に花を育てられないのであれば、必ず使う土は「花の培養土」「花と野菜の培養土」のように肥料が配合済みの培養土を購入して下さい。
培養土は花が成長するために最も適したブレンド用土なのでこれ1つあればうまく栽培できます。
安い土を使っている
激安だったり百円均一で販売されている土はできれば避けましょう。肥料成分が含まれていなかったり軽すぎたりして成長をはばむケースがあります。
対処法
必ず「培養土」で育てましょう。今もし安い土を使っていて生育が悪いのであれば交換をおすすめします。
毎年同じ土を使っている
毎年使い古された土を使っても栄養分がなかったり病気に感染していることもあるので、花が枯れる原因になります。
対処法
古い土を再生させる土も販売されていますが、限度があります。元々が悪い土に再生土を入れても意味がないこともあります。
思い切って新しい培養土を購入しましょう。
鉢底石を敷いていない
排水システムのないプランターに鉢底石を敷かずいきなり培養土を入れると、排水が悪くなり植物の根が腐ります。
対処法
排水の問題と大きく関係していますが、排水システムのないプランターで栽培する場合、まず鉢底から高さ3㎝程度軽石などの鉢底石を敷き詰めその上に培養土を入れていきます。
水やりの問題

季節に関係なく毎日水やりをする
子供の頃の夏休みの宿題に「花の水やり」があったと思いますが、夏も冬も関係なく土の状態を観察せずにただ日課として毎日花に水をやると根が腐り枯れます。
よく毎日水やりしないとかわいそうだからと言われますが、それはお腹いっぱいの人に無理やり食べさせ続けるのと同じです。
対処法
鉢土が乾燥しているときのプランターの重さと水をたっぷり与えたときの重さを比較し、乾燥しているときの重さに近くなった時が次の水やりのタイミングです。
ただし、植物の状態を見て判断して下さい。
毎日観察していれば水が足りているか不足しているかは植物の状態からわかるようになります。最適な水やりのタイミングは体感でしか覚えられないのでぜひ訓練しましょう。
鉢土の表面が乾いたらたっぷりあげている
ネットでも本でも水やりの基本は「鉢土の表面が乾いたらたっぷりあげている」と書かれていますが、表面だけが乾いていて実はプランターの中の方は乾いていないことがあります。
それを知らずに水をやり過ぎることで枯れます。
対処法
前の項目で紹介した鉢の重さを比較する方法や植物の状態を観察するほかに、実際に掘って中の方の土を触って乾燥しているかどうかを確認する方法があります。
ただ、棒などを刺して調べても初心者には乾いているかどうか判断が付かないので体感で覚えるしかありません。
水やり時に鉢底から水が出るまでやっていない
室内で花を育てている場合、鉢の底から水が出てお皿から溢れちゃったら困るからあまりたくさん水はやらない人がいます。鉢底から水がでるまでたっぷり与えないと鉢内に汚い空気がたまり、うまく花が成長しません。
対処法
水やりの目的は水不足解消だけでなく、鉢内にたまっている汚れた空気を押し出す換気の役割を持っています。
必ず水やりは鉢底からしっかり出るまで与え、室内栽培など鉢皿を利用している場合は水をためないように捨てて下さい。
肥料の問題

肥料ではなく活力剤をやっている
肥料と活力剤、どちらも同じように感じますが全く違います。人間で例えると肥料は食事やクスリ、活力剤はサプリや栄養ドリンクです。肥料は植物の成長を元から助けるものですが、活力剤はあくまでも一時的に成長をうながす補助的なものです。
よく土に以下写真のようなアンプルを刺している人がいますが肥料ではなく活力剤です。

対処法
基本的に培養土に肥料成分が配合されているので3ヶ月程度は新たに肥料をやらなくても枯れることはありません。
しかし、植物も次から次へと花を咲かせるにはパワーがいるため、2週間に1回程度水やりをかねて液体肥料を混ぜて与えると良いでしょう。
活力剤をやるなら肥料にプラスして与えます。
分量をテキトーにやっている
肥料はやり過ぎても肥料焼けといって植物の根をダメにしてしまいます。たくさんあげた方が元気になるのではないか?と思ってやる人がいますが枯れる原因なのでやめましょう。
対処法
液体肥料や固形肥料は必ずパッケージに記載された分量を守って与えて下さい。
肥料を全くやらない
プランター栽培は花壇や地植えなどと異なり水やりの度に肥料成分も流れ出て行くので、定期的に肥料を与えないと栄養分が不足し成長が鈍くなります。
対処法
実は3ヶ月程度であれば肥料を全く与えなくても花数は減りますが、枯れることはありません。肥料が原因で枯れる場合はやらないよりもやり過ぎて枯らしてしまう方が圧倒的に多いです。
ただし、肥料は植物にとって大事な栄養源なのでぜひ与えて栽培しましょう。
置く場所の問題

植物の生育環境と合っていない
シダ植物など日陰を好む植物なのに日当たりに置いていたり、ヒマワリなど日光を好むのに日陰においていると成長が悪くなります。
対処法
よく玄関が北向きや西向きで植物が育たないというお悩み相談を受けますが、そのようなときはプランターを2つ用意し、日向と日陰にそれぞれ置いて2週間に1回くらい交互に場所を交換して飾りましょう。
メインで飾りたい場所が北や西向きであればこのような方法があります。もし全く日が当たらない家であれば日陰に強い植物やカラーリーフなどを楽しむ方法があります。
エアコンの風や室外機の風が当たっている
室内栽培でも屋外栽培でも人工的な温風や冷風が休むことなく継続して当たるため植物をダメにしてしまいます。
室外機の上に置くのもやめましょう。風が上がってきて植物を痛めます。
対処法
植物の成長には「ゆらぎ」といってある程度風に当たることも上手く成長する条件の1つなので、観葉植物などは定期的に葉を拭いたりすることで「ゆらぎ」を再現できます。
よく話しかけたり触ったりすると元気になるなんてスピリチュアルなことを言う人がいますが、この「ゆらぎ」が関係しています。あとはそれだけよく観察しているので少し変化があった時に早く対処できているともいえます。
病気害虫の問題
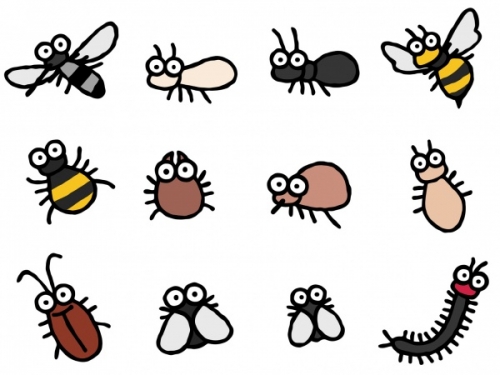
風通しが悪い場所で育てている
例えば、木や草がうっそうとしている場所やジメジメしている場所で育てると風通しが悪いのでカビなどの病気や害虫の被害にあいやすくなります。
対処法
置き場所の問題とも関係しますが、日陰を好む植物でない限りできるだけ風通しの良い日光があたる場所で育てましょう。
殺虫殺菌対策をしていない
病害虫はかかる前の対策とかかってしまった後の対処をどれだけきちんと行うかによってその後の植物の成長に関係します。
対処法
病害虫対策にはあらかじめ土にまいておく薬剤もありますし、被害に遭った後にはスプレータイプの殺虫殺菌剤も販売されているので被害が広がらないように早めの対策をする必要があります。
植物の生理現象の問題

花屋さんで咲いていた時はキレイだったのに買ってきた翌日に葉っぱが黄色くなったり、葉が落ちてしまうことがあります。
これは植物が新しい環境に移ったためあえて自分から葉を落としエネルギーを温存し環境に耐えようとする生理現象です。
ゼラニウムなどの葉が3日程度で真っ黄色になったりウンベラータなどの観葉植物が葉を落とすなどの原因は生理現象が関係しています。ウンベラータは寒さに弱いので冬は葉を落とし春にまた芽吹きますがこれも生理現象です。
対処法
生理現象に関してはどうすることもできません。売られていた環境と同じ環境を再現すれは良いですがなかなか難しいのが現実です。
ただし温室栽培が必要なバンダなど一部のラン類や湿度を好むコウモリランやマルハチヘゴのような一部の栽培難易度が高いシダ類観葉植物を除き、買ってきて、生理現象によってそのまま根まで枯死してしまうことはまずありません。
根が死んでいなければまた新しく新葉がでますので待ちましょう。
植物はそれぞれの原産地と似た環境であれば日本でもちゃんと成長することができます。
▼この記事の読者は以下の記事も読んでいます▼
トマト栽培特集!
イチゴの月別!栽培方法
| 10月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| | 11月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |
| 12月1月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 冬のイチゴの育て方! 2月の時期の作業と栽培方法 | |
| 3月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 4月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| | 5月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |
| 6月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 7月8月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |
| 9月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |